和歌山の少年から国際ビジネスマンへの軌跡
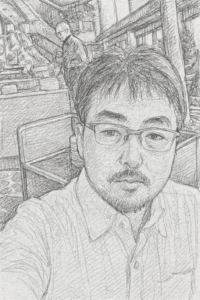 プロローグ──人生は予測不可能な冒険である
プロローグ──人生は予測不可能な冒険である
人生を振り返ると、まるで一本の映画のように思える。和歌山の小さな町で生まれた少年が、どうして上海で起業し、香港に法人を構え、スリランカ政府の特命大使になったのか。衆議院選挙に出馬し、両目の視力を失いかけ、そして奇跡的に回復する──この物語は、私自身が生きてきた現実そのものである。
この半生記は、単なる自己紹介ではない。これは、「人生には不可能なことなどない」という信念を証明する記録であり、「直感と行動力があれば、運命は切り開ける」という実践の記録である。
第一章:幼少期──和歌山の海と山に囲まれた少年時代(1973年~1986年)
海南市という故郷
1973年、私は和歌山県海南市という人口約5万人の小さな町で生まれた。海南市は和歌山県の北部に位置し、海と山に囲まれた自然豊かな地域である。和歌山県は県面積の約80%が山地という日本でも有数の山岳地帯であり、私の育った海南市も例外ではなかった。
私の家は高台にあり、そこから見下ろすと貴志川という川が流れていた。幼少期の記憶の中では、夏になるとこの川で泳いだことが多く、海水浴の思い出よりも川遊びの思い出の方が強く残っている。海に囲まれた町でありながら、山側で育った私にとって、川が最も身近な自然だったのである。
公務員一家という環境
私の家族は、いわゆる公務員家庭だった。父は和歌山県庁職員、母は幼稚園の先生を経て農協(JA)に勤務、祖母は海南市役所職員という、安定した公的機関に勤める家系だった。
特に興味深いのは祖父の経歴である。彼は少年兵として海軍に入り、海軍兵学校の教官を務めていた。さらに、戦時中には特攻隊関連の業務にも携わっていたと聞かされている。しかし、戦争が終わるとGHQ(連合国軍総司令部)による追及を恐れ、約10年間消息を絶っていたという。家族の話では、おそらく九州の炭鉱などで身を隠しながら働いていたのではないかと言われている。
この祖父の経歴は、後に私が東京商船大学(現・東京海洋大学)を選ぶ際の潜在的な影響となった。海軍と商船学校──このつながりは、私の人生の選択に見えない形で作用していたのかもしれない。
「悪ガキ」としての小学校時代
地元の公立小学校である中野上小学校に進学した私は、次第に「問題児」としての道を歩み始めた。特に小学校6年生の頃には、いわゆる「悪名高い3人組」の中心メンバーの一人となり、学級崩壊を引き起こすまでになった。
先生に対して反抗することも多く、私たちの行動が原因で担任の先生が転勤になってしまったという事実は、今振り返っても大きな反省点である。しかし、この時期に学んだことがある──それは、「集団を動かすには強いリーダーシップが必要だ」ということだった。
野球部に所属していたが、私のチームは弱小チームで、ほぼ毎回1回戦敗退という惨憺たる成績だった。しかし、この経験が私に「勝つためには何が必要か」を考えさせるきっかけとなった。
第二章:中学時代──荒れた学校で生き抜く術を学ぶ(1986年~1989年)
東海南中学校という戦場
地元の東海南中学校に進学した私を待っていたのは、まるで北斗の拳のような世界だった。当時はビーバップハイスクールやヤンキー文化が全盛期で、学校は頻繁に荒れていた。「こんな中学生、本当にいたのか?」と思うほど、手のつけられないような生徒が数多くいた。
この環境で生き残るため、私は筋力トレーニングにのめり込んだ。陸上部のキャプテンとして投てき競技(砲丸投げ・円盤投げ)に打ち込む一方で、実際には「地元で喧嘩に負けないために」体を鍛えていたという側面が強かった。
生徒会長という矛盾
驚くべきことに、私は問題児でありながら生徒会長にも立候補し、当選した。私の生徒会運営は独特で、体育祭の運営を学校の悪ガキたちに任せるという手法を取った。結果として、彼らが仕切ることで驚くほどうまく運営でき、先生たちからも評価された。ただ、実態は「恐怖政治」に近かったかもしれない。
この経験を通じて学んだのは、「集団を統率するには強いリーダーシップが重要だ」ということだった。そして、もう一つ重要な学びがあった──それは、「結果を出せば文句は言われない」という社会の現実である。
「成績が良ければ許される」という矛盾
私は問題児だったが、進学塾に週6日通っていたため、成績は学年5位以内に入っていた。そのため、先生たちは私に対してあまり厳しく叱ることはなかった。
この矛盾した対応を目の当たりにし、私は子供ながらに「結局、社会は結果重視であり、結果さえ出せば許される」ということを学んだ。この認識は、後の人生で大きな影響を与えることになる。
第三章:高校時代──進学校での競争と新たな選択(1989年~1992年)
近畿大学附属和歌山高等学校への進学
私は近畿大学附属和歌山高等学校に進学した。この学校は地元では進学校として知られ、「現役で国立医学部を目指せ」という教育方針のもと、難関大学を目指す生徒が多い環境だった。
高校入試では約2000人の受験者の中で上位25位という成績で合格し、最も学力の高い「アドバンスクラス」に入った。しかし、このクラスに入ると、それまでの「努力すれば勝てる」という感覚は通用しなかった。クラスメイトは地元だけでなく、大阪南部などの進学塾で鍛えられた優秀な生徒たちだった。
東京商船大学という選択
高校3年生の進路決定の時期、私の親から「現役で国立大学に入学したら車を買ってあげる」と言われた。この言葉に惹かれて現役合格できる国立大学を探した結果、最終的に選んだのが東京商船大学(現・東京海洋大学)だった。
この選択には複数の理由があった。まず、祖父が海軍で活躍していた影響で、幼い頃から海の世界に興味があった。次に、理系の成績は良かったが、研究者には向いていないと感じていた。そして、少し変わった分野を学びたいという思いがあった。
この選択が、後の人生を大きく変えることになる。
第四章:大学時代──上京、アルバイト、そして中国との出会い(1992年~1997年)
東京という大都会
和歌山の田舎から東京の大都会に上京した私は、最初は右も左も分からず、東京での生活に慣れるのに時間がかかった。最初に住んだのは東京都江戸川区の葛西で、ここから私の東京暮らしが始まった。
大学時代の思い出を振り返ると、学業よりもアルバイトに時間を費やしていた。居酒屋、串カツ屋、ドーナツ屋、宅配ピザなど、様々な仕事を経験した。特にドーナツ屋では相当気合を入れて働き、店長から「アルバイト店長にならないか?」と言われるほどだった。
中国人留学生との出会い──運命の転換点
大学生活で最も影響を受けたのは、中国人留学生たちとの出会いだった。私は子供の頃、父が日中国交正常化後の「友好の船」プロジェクトで中国を訪れた話をよく聞いていた。この影響もあり、いつか中国に行ってみたいと考えていた。
当時の中国(1990年代前半)はまだ経済発展が進んでおらず、貧しい時期だった。日本に正規留学している中国人学生たちも、決して裕福な家庭の出身ではなく、必死に勉強していた。しかし、彼らの多くは非常に優秀な人材であり、「こんなに優秀な人がいるのに、なぜ中国はまだ貧しいのか?」という疑問を抱くようになった。
中国人の学生に話を聞くと、「中国は国家の体制によって、若者がチャンスを掴みにくい。だから海外に出るしかない」と言っていた。さらに、中国の社会構造についても知ることになる。家系(出身階層)がすべてを決め、生まれた家のバックグラウンドによって将来が決まるという現実。いい家に生まれれば良い人生が待っているが、そうでなければ努力しても報われない。海外に出ることが人生を変える唯一の方法だという。
この話を聞いて、「中国という国は一体どんな国なのか?」という興味が一気に強まった。
中国留学の決断
ある日、大学の学生課の前を歩いていた時、「日中友好協会──中国の大学に留学しませんか?」という掲示板を偶然見つけた。興味を持ち、すぐに電話して問い合わせた結果、上海に留学することを決めた。
どの大学がいいのか分からなかったが、「上海なら楽しい学生生活が送れるだろう」「男ばかりの学校より、女子が多い大学の方がいい」という単純な理由で、上海師範大学を選んだ。この直感的な決断が、私の人生の方向を決定づけることになる。
第五章:上海留学時代──言葉よりも経験で学んだ2年間(1997年~1999年)
上海師範大学での生活
1997年、私は上海師範大学に留学した。この2年間は、単なる語学学習ではなく、中国という国を体験し、現地の文化を深く知る時間となった。
留学の目的はもちろん中国語の習得だったが、教科書だけでは身につかないことも多く、私は「実践の場で学ぶ」という方法を選んだ。毎日大学の正門で学生の女の子をナンパし、とにかく会話の機会を増やすことを実践した。
ナンパをしていると、フランス人の留学生が興味を持ち、「お前たちは何をしているんだ?」と聞かれ、私が「中国語を学ぶためにナンパしている」と答えると、「じゃあ俺も混ぜてくれ!」と言われ、ここで国境を越えた友情が芽生えた。
ダークな中国──表と裏の世界
留学中、私は上海という都市の表の部分だけでなく、裏の世界にも足を踏み入れた。怪しいナイトスポット、裏社会のネットワーク、インターネットでは書けないようなディープな中国──こうした場所に出入りしていると、現地の中国人からも「お前たち、よくそんな所に行くな」と言われることが増えた。
この経験を通じて、中国の光と影の両方を見ることができたのは、私にとって貴重な学びだった。そして、この経験が後の貿易ビジネスにおいて、「中国の実態を知る人間」としての強みとなった。
中国ビジネスへの興味
留学中、私は「どうすれば中国と日本をつなぐビジネスができるのか?」を考え始めた。そして、中国人の友人と協力し、個人輸入代行業を始めた。日本では手に入らない中国の商品を仕入れ、日本で販売する小さなビジネスだったが、この経験が後に貿易コンサルティングを始めるきっかけとなる。
第六章:社会人時代──日本企業での経験(1999年~2003年)
トランスコスモスでのITスキル習得
1999年、大学を卒業した私はトランスコスモス株式会社に就職した。この会社は東証一部上場のITソリューション企業であり、私の出身地である和歌山県発祥の企業でもあった。
入社後、私は開発部門で働くことになり、パソコンを使ったインターネット関連の研究、ホームページ制作の基礎を学んだ。この時に習得した知識は、後のビジネスでも大いに役立った。実際、今でも私は自分のビジネスのホームページを全て自作している。
しかし、開発の仕事がつまらなく感じるようになり、営業部門へ異動した。だが、「中国で仕事をしたい」という目標があったため、「いつ中国に派遣されるか分からない」という状況に不安を感じ、次のキャリアに進むために退職を決意した。
NTTでの営業経験──「国営企業ブランド」の強さ
トランスコスモスを退職後、つなぎの仕事としてNTTの営業職を選んだ。当時、日本の通信業界では電話回線の民営化が進んでおり、NTTユーザーに対して「マイライン登録」の営業活動が行われていた。
私はこの営業担当として働いたが、「NTTです」と言うだけで、誰もが話を聞いてくれることに驚いた。特に田舎では、「NTT以外の選択肢がある」ということ自体を知らない法人が多かった。そのため、私は特に苦労することなく営業成績を上げることができ、一時期は全国表彰されるほどの営業成績を記録した。
この経験から、「ブランドの力は絶大だ」ということを実感した。
中国塗料での船舶業界経験
2001年、ついに私は中国での社会人生活をスタートさせることができた。日本の東証一部上場企業である中国塗料の上海現地法人に就職したのである。
私が担当したのは、船舶の塗装に関する営業および管理業務だった。造船所を回り、塗料の販売、船の修繕・新造時の塗装管理、現場監督として塗装作業のチェックなどを行った。
この業界では、東京商船大学の卒業生というだけで信頼を得やすいというメリットがあった。業界内では学閥が非常に強く、先輩後輩の関係がビジネスに直結する世界だった。
しかし、仕事環境の過酷さ(塗料のシンナーによる健康リスク)と、人間関係の難しさ(成果を出しても学閥の壁で評価されない)により、最終的には退職することになった。
高砂倉庫での物流改革
中国での2社目として、私は上海の外高橋保税区にある福岡県の物流倉庫会社「高砂倉庫」に就職した。入社してすぐに気づいたのは、社内が完全に崩壊していることだった。チームワークが全くなく、社員の仕事意識が低く、ミスが多発していた。
私はこの崩壊した体制を立て直すことをミッションとし、4〜5ヶ月で業務の改革に成功した。さらに、取引先との価格交渉でも「喧嘩殺法」とも言える強気の交渉を仕掛け、値上げ交渉に成功した。
しかし、私が改革を成功させたことで、3年間問題を放置していた専務が嫉妬し始め、最終的には喧嘩別れのような形で退職することになった。
第七章:起業と中国ビジネス黄金時代(2004年~2013年)
2004年──上海での独立
2004年、私は上海の物流倉庫会社を退職し、ついに起業することにした。起業の最初のきっかけは、上海で知り合った日本企業の駐在員からの依頼だった。「中国のメーカーと取引をして、自動車メーカー向けの金属製ラックを上海の工場で生産したい」という案件を手伝うことで、最初のビジネスをスタートさせた。
ホームページを活用した集客戦略
最初の取引先は1社だけだったが、私はすぐに「もしこの会社が取引をやめたら終わりだ」と危機感を持った。そこで、インターネットを活用することにした。
私はトランスコスモス時代にITを学んでいたので、ホームページの作成、ウェブマーケティングに関する知識を持っていた。ポータルサイトに顔写真入りのバナー広告を掲載し、知名度を上げる戦略を取った。海外では「信用がない」のが当たり前なので、「顔を出しておけば、少しでも信用が上がるだろう」と考えた結果だった。
動画マーケティングの先駆け
現在ではYouTubeを活用した動画マーケティングは当たり前だが、2004年当時はYouTubeすら存在しない時代だった(YouTube創業は2006年)。私は自前のサーバーに動画をアップロードし、ストリーミング配信を実施していた。
「中国現地の情報を動画で見られる」というのは非常に珍しく、これが大きな反響を呼んだ。特に2006年頃から始まった「上海進出ブーム」の影響で、日本全国から多くの企業が中国市場に興味を持つようになった。
セミナービジネスの展開
貿易コンサルティング会社として、私は中国ビジネスセミナーを開催するようになった。2006年から2010年にかけて、日本全国および中国各地で毎週のようにセミナーを開催し、約3,500社の企業、約3,500名の個人受講者に対して、中国市場の現状、貿易実務、法規制、成功事例、失敗事例などを詳しく解説した。
特筆すべきは、これらのセミナー集客をすべて自身のインターネットブログやメールマガジンを通じて実施した点である。当時としては先進的なデジタルマーケティング手法を駆使し、全国から参加者を集めることに成功した。
北京大学での快挙
中国ビジネスの専門家としての認知が広がる中で、私は大学での講義の依頼も受けるようになった。特に印象的だったのが、「北京大学のエグゼクティブMBAプログラムで講師を務めたこと」である。
私は大学時代、卒業論文で「中国経済」をテーマにしようとしたとき、教授に却下された過去がある。「お前は東京商船大学の学生なのに、なぜ中国経済の論文を書きたいんだ?却下!」と言われた。結局、「船舶の揺れによる危険物の爆発リスク」という、興味もないテーマで論文を書くことになった。
しかし、その私が、後に北京大学で貿易の講義をすることになったのである。この瞬間、私は「やればできるじゃないか」と自分自身を誇りに思った。
2012年──尖閣諸島問題と中国ビジネス黄金時代の終焉
順調に見えた中国ビジネスだったが、2012年に転機が訪れた。尖閣諸島の漁船衝突問題をきっかけに日中関係は一気に悪化した。同時に、中国政府の規制も厳しくなり、日本企業の進出が減少、中国ビジネス環境が悪化するという状況になった。
私の周りでも、多くの日本人経営者がベトナムなど東南アジアに移住する流れが加速した。結果として、「上海ビジネスの魅力」が大きく低下していった。
第八章:2012年衆議院選挙への挑戦(2012年)
なぜ政治の世界へ?
2012年は、私にとって大きな転機となった年だった。それまで上海でビジネスを展開していたが、「日本で新しい挑戦をするべきではないか」と考え、衆議院選挙に出馬するために日本へ帰国する決断をした。
私が政治に興味を持ったのは、日本経済の衰退や国際的な立場の低下を目の当たりにしたからである。特に、中国でのビジネスを通じて、日本企業の競争力の低下、海外市場での日本の影響力の減少を強く感じていた。
福岡2区からの出馬
最初は自民党から出馬を希望したが、「支部長になるのは無理」と門前払いされた。最終的に、民主党が「国民の生活が第一」という新党に分裂した際、偶然にも民主党側の事務局長が私の友人だったため、そこから出馬することになった。
私が立候補したのは福岡2区で、福岡市の中心部(中央区・南区・城南区)を含む都市型の選挙区だった。しかし、私は福岡出身ではなく、完全な「落下傘候補」だった。そのため、地元の人脈もなく、ゼロからのスタートとなった。
選挙戦と結果
2週間の選挙戦の結果は惨敗だった。しかし、選挙に出ることで、政治の裏側を知ることができた、日本の選挙システムを理解できた、多くの新しい人脈を得ることができたという点では、大きな経験となった。
選挙後、「もう一度、同じ選挙区で戦うか?」と考えたが、福岡に地盤がなかったこと、政治活動を続けるリソースがなかったことなどの理由から、一度選挙の世界から離れる決断をした。
第九章:試練の時──両目失明の危機(2013年~2014年)
2013年9月19日──視力を失った日
2013年9月19日、私は突然、両目の視力を失った。神奈川県藤沢市のファミリーレストランで友人と食事をした後、帰宅しようとしたその時、突然、両目の視界が真っ暗になったのである。
最初は驚いたが、かろうじて視界の半分がぼんやりと見えていたため、なんとか車を運転し、自宅まで戻ることができた。しかし、今考えれば、視力がほぼない状態で車を運転するというのは異常なことだった。家に到着した頃には、完全に視界がブラックアウトしていた。
過酷な治療の日々
翌日、神奈川県海老名市にある海老名総合病院へ向かった。診察室に入ると、医師は私の目を一瞥しただけで、「これは手の施しようがない」と言い放ち、わずか1秒で診察室を出て行ってしまった。
その後、妻がインターネットで徹底的に調べた結果、横浜に評判の良い眼科があることがわかり、すぐにその病院へ向かった。診察の結果、レーザー治療と手術が必要だと言われた。
レーザー治療は想像以上に激痛だった。しかし、視力を取り戻すために耐え続けるしかなかった。その後、東京医療センター(目黒区)へ緊急搬送が決まり、人生初の手術を受けることになった。
奇跡的な回復
手術直後、医師たちは「完全には治らないかもしれない」と話していた。しかし、1年半の治療とリハビリを経て、奇跡的に視力が回復した。現在、矯正視力ではあるが、1.0まで回復している。
失明の恐怖から学んだことは計り知れない。「人生で一番きつかった経験は?」と聞かれたら、間違いなくこの時期と答える。目が見えないということは、仕事ができない、家族の顔が見えない、一人では外出できないという状況になり、「自分の人生が終わった」とすら思った。
しかし、医療の力、家族の支え、自分の気力で乗り越え、今こうして普通に生活できていることに心から感謝している。
第十章:新たな挑戦──不動産と貿易の融合(2015年~現在)
2015年──東京不動産会社の創業
2015年、私は東京で新たなビジネスをスタートさせた。それが不動産事業である。妻が「宅地建物取引士(宅建)」の資格試験に合格したことがきっかけだった。
東京都港区赤坂に不動産会社を登記し、本格的に業務をスタートさせた。実は、私自身に不動産の経験は全くなかったが、インターネットを活用した集客戦略により、徐々に顧客が増え、物件の売買もできるようになった。特に印象的だったのは、2億円を超える一棟マンションの売却に成功したことである。
私は海外生活が長かったこともあり、外国人投資家とのつながりがあった。そこで、日本の不動産に興味を持つ外国人投資家へも物件を紹介するようになった。2015年以前は主に中国人投資家からの相談が多かったが、2020年以降は中国市場が落ち着き、東南アジアなどの新興国投資家が増加している。
2016年──日本法人の再設立と貿易事業の再開
2016年、私は再び日本で事業を展開することを決意し、貿易商社として法人を設立した。主に中国からの建築資材の輸入を行う貿易事業を中心に活動を開始した。
なぜ足立区で起業したのか? 東京での創業場所を考えていた際、意外にも「足立区が創業支援に力を入れている」ことに気づいた。さらに、足立区には建築関連の業者が多く、事業の展開に適した環境であることが分かった。
そこで、足立区の「創業支援制度」を活用し、正式に法人を設立した。最初のオフィスは、足立区の公的なインキュベーション施設「かがやき」にある事務所を借り、ビジネスをスタートさせた。
具体的には、中国で建築資材を発注、コンテナ輸送にて日本へ輸入、日本の建築現場に納品というビジネスモデルを展開した。このビジネスモデルは、上海時代の貿易業務の延長線上にあったため、中国の工場ネットワークを活用し、スムーズに事業を進めることができた。
香港法人の再設立
事業の拡大に伴い、2016年には香港に現地法人を再設立した。私が香港で法人を設立したのは、これで2度目である。最初の設立は2006年だったが、2016年に完全に独立した形で新たな香港法人を設立することを決断した。
香港法人を活用する理由は明確だった。中国貿易のゲートウェイとして、中国と海外の資金移動には厳しい規制があるため、香港を経由することで資金管理がしやすくなる。また、キャピタルゲイン税の非課税、国際送金の利便性、オフショア企業としての活用など、多くのメリットがあった。
第十一章:精神世界との邂逅──見えない世界のつながり
2005年──法然上人の夢枕
2005年頃、私は上海での仕事の合間に一時帰国し、日本で不思議な体験をした。それは、ある意味で「日中の架け橋」となる運命を予言されていたかのような出来事だった。
神戸の社長の紹介で出会った祈祷師から、「あなたの家の北側にある何かがあなたを呼んでいる」と言われた。私はピンときた。「私の実家の北側には、うちの家系のお墓があります」。
実家に帰り、仏壇の前で手を合わせた瞬間、何かがパッと通り過ぎる感覚があった。その時、心の中で「左の仏像の人が来ましたね」と思った。すると父が、「その仏像は、法然上人だ」と言った。
その夜、私は夢の中で法然上人と出会った。彼は私にこう語りかけた。「私は南無阿弥陀仏を学びましたが、中国に行ったことがなかった。だから、あなたに行ってもらいました。南無阿弥陀仏を唱えて、日中の平和を祈ってください」。
翌日、船井総研という大手コンサルティング会社から突然連絡があった。「上海で法人を設立したいが、美容室の営業許可がなかなか降りないので助けてほしい」という相談だった。この依頼をきっかけに、中国でのコンサルティング事業を本格的に始めることになった。
2007年──マハリシとの出会いと通貨発行権への関心
2007年、私はTM瞑想(超越瞑想)関連の企業のコンサルティングを担当していた。その際、ビートルズにTM瞑想を指導したことで世界的に知られたマハリシ・マヘーシュ・ヨーギーから、「通貨発行について研究しなさい。そして貿易についても行いなさい」という予言的なメッセージを受けた。
マハリシ先生が上海の私のオフィスに直接電話をかけてきたのである。瞑想を普及させることはTMの理念として理解できたが、なぜ通貨発行なのか? その時はよく分かりませんでしたが、先生の言葉が引っかかり、そこから金融・国際経済の研究を始めるきっかけになった。
マハリシ先生との会話の約半年後、彼はこの世を去った。しかし、彼の言葉は私の中で生き続け、その後15年間にわたり国際金融・通貨発行権についての探究を続けることになった。現在は、ODA開発援助事業、国際非営利財団との連携、世界各国への資金提供プロジェクトなど、グローバルな金融システムの変革に関わる仕事をしている。
パワースポット巡り──日中の精神世界を旅する
2002年から2013年にかけて、私は日本と中国の仏教遺跡やパワースポットを巡る旅をしていた。日本の多くの仏教僧が修行のために中国へ渡った歴史を知り、私自身も長年中国で暮らしていたこともあり、時間があれば日本の僧侶が修行した中国の寺院を巡っていた。
山東省の泰山では、歴代皇帝が即位式を行った聖なる山で「皇帝のパワー」を感じた。浙江省の国清寺では、日本に仏教を伝えた鑑真や道元が修行した寺に泊まり、不思議な夢を見た。山西省の五台山では、文殊菩薩の霊場で別次元にいるような神秘的な感覚を体験した。
こうした体験を通じて、私は「パワースポットは、単なる観光地ではない。そこには歴史・宗教・エネルギーが交差する深い意味がある」ということを学んだ。
第十二章:国際的な展開──スリランカとの架け橋(2020年~現在)
スリランカ政府の特命大使就任
2020年、私はスリランカ政府の文部省「職業訓練庁(Vocational Training Authority)」の特命大使という資格を与えられ、スリランカと日本の架け橋としての役割を担うことになった。
ある知人の紹介で、スリランカ政府の文部省職業訓練庁の長官と知り合った。彼からの依頼は、スリランカと日本の関係を深めたい、スリランカの人材を日本の企業で働けるようにしたい、日本企業の進出を促し、スリランカ国内での雇用を増やしたいというものだった。
スリランカは2022年に国家財政破綻を宣言し、深刻な経済危機に陥っている。外貨不足により、燃料・医薬品・食料の輸入が困難になり、若者の就職難も深刻化している。しかし、スリランカは親日国として長年の友好関係を維持しており、日本からのODAや民間投資への期待が大きい。
今後の展開として、日本企業向けの進出サポート、スリランカ人材の日本企業へのマッチング、貿易事業の拡大などの可能性を模索している。スリランカとの貿易・人材交流を強化し、スリランカと日本の関係強化を目指している。
第十三章:現在の事業展開と今後のビジョン
多角的なビジネスポートフォリオ
現在、私は複数の事業を同時に展開している。東京都港区を拠点とした不動産事業では、海外投資家向けの日本不動産投資サポートを中心に、売買仲介、賃貸管理、投資コンサルティングを提供している。
貿易事業では、HONG KONG JCBO LIMITEDを通じて、中国からの建築資材輸入、日本企業の中国進出支援、三国間貿易のコーディネートを行っている。特に建築資材分野では、日本の建材高騰という課題に対して、中国工場からの直接調達という解決策を提供している。
国際コンサルティング事業では、香港法人設立サポート、中国ビジネスリモートサポート、スリランカ進出支援など、アジア全域をカバーするサービスを展開している。
中国建材市場の最新動向研究
2024年以降、私は中国建材市場の最新動向を継続的に研究し、情報発信している。中国の住宅建材業界における海外輸出の急増、地方政府主導の産業支援政策、国産ブランドの台頭、グリーンビルディングへの転換など、重要なトレンドを把握し、日本企業へのアドバイスに活用している。
中国国家建築材料グループのような大手企業の動向、山東省などの地方政府による産業変革計画、個別企業の成功事例など、多角的な視点から中国建材市場を分析している。
日本経済再生への貢献
私は、単なるビジネスの成功だけを目指しているわけではない。日本経済再生機構および地方創生支援機構という民間シンクタンクを立ち上げ、経済政策の提言や地域経済活性化に向けた取り組みを進めている。
長年海外で生活してきた経験から、経済力は国際的評価に直結することを深く理解している。現在の日本は、世界経済における地位が年々低下し、海外では「日本は終わった」との厳しい評価が広がりつつある。こうした状況に対し、「このままではいけない」という強い危機感を抱いている。
海外から日本が再び高く評価され、国民が誇りを持てる社会の実現に向けて、経済活性化に寄与する事業に取り組んでいる。
今後のビジョン──グローバルとローカルをつなぐ
これまでの25年間、私は日本と中国、そしてアジア各国を結ぶ「架け橋」としての役割を果たしてきた。今後もこの役割を継続し、さらに発展させていきたいと考えている。
具体的には、以下の3つの方向性を重視している。
①日本企業の国際競争力強化
中小企業を中心に、海外調達、海外進出、海外販路開拓を支援し、グローバル市場での競争力を高める。
②アジアの成長力を日本に取り込む
中国、東南アジア、南アジアの経済成長の恩恵を日本に取り込むため、貿易、投資、人材交流を促進する。
③次世代への知識の継承
20年以上にわたる国際ビジネスの経験と知見を、次世代の起業家やビジネスパーソンに伝え、日本の国際競争力向上に貢献する。
エピローグ──「思考は現実化する」という信念
私の座右の銘は「思考は現実化する」である。これはナポレオン・ヒルの名著から影響を受けたもので、明確なビジョンと強い信念を持ち続けることで、必ず目標は達成できるという考え方を表している。
振り返れば、私の人生は常に「直感」と「行動」によって切り開かれてきた。上海師範大学を選んだのも、「女性が多い大学の方が楽しそう」という単純な理由だった。北京大学で講義をすることも、衆議院選挙に出馬することも、両目の視力を失いながら回復することも、すべて予測不可能な出来事だった。
しかし、その一つ一つが、私という人間を形成し、今のビジネスにつながっている。法然上人の夢、マハリシからのメッセージ、中国人留学生との出会い──これらすべてが、見えない糸で結ばれているように感じる。
人生には、目に見えない導きが確かに存在する。そして、その導きに従いながらも、自分自身の意志で行動することが重要だ。「寧静至遠(静かなる心こそ遠くへ至る)」という中国の古典的な言葉のように、落ち着いた心と冷静な判断力を持ちながら、遠大な目標に向かって進み続けること──これが私の生き方である。
読者へのメッセージ
この半生記を読んでくださった皆様へ。もしあなたが今、人生の岐路に立っているならば、あるいは新しい挑戦を躊躇しているならば、私の経験が少しでも参考になれば幸いである。
人生において試練は避けられない。しかし、すべてを懸けて成し遂げるべきことがある。運命は変えられないかもしれないが、それを示す羅針盤から逃げることなく歩み続ければ、必ず光が差す。継続こそが成長を生む。
私の物語はまだ終わっていない。これからも、日本と世界を結ぶ架け橋として、新たな挑戦を続けていく。そして、その経験を通じて得た知見を、次の世代に伝えていきたいと考えている。
皆様も、自分自身の直感を信じ、恐れずに一歩を踏み出してほしい。そこには必ず、新しい世界が待っている。
第十四章:2024年以降──新たな時代の架け橋として(2024年~現在)
時代の転換点──中国企業の日本進出という新潮流
2024年以降、私のビジネスは新たな局面を迎えている。これまで20年以上にわたり、日本企業の中国進出を支援してきたが、現在はその逆──中国企業の日本進出支援という、まったく新しいステージに入っているのである。
中国起業家が日本を目指す理由
かつて、中国は「世界の工場」として、日本企業が進出する先だった。しかし、時代は大きく変わった。中国経済の成熟化、不動産市場の低迷、若者の起業意欲の高まり、そして何よりも「日本市場の魅力」の再発見──これらの要因が重なり、優秀な中国人起業家たちが日本に進出してくるケースが急増している。
彼らが日本を選ぶ理由は明確だ。日本は政治的に安定しており、法制度が整備され、知的財産権が保護されている。中国国内の不確実性が高まる中で、日本は「安心してビジネスができる場所」として再評価されているのである。
また、日本の消費者市場は成熟しており、高品質な製品やサービスへの需要が高い。中国で成功した起業家たちにとって、日本市場は次なる挑戦の場として魅力的なのだ。
中国企業日本進出支援の実務
私が提供している中国企業向けの日本進出支援サービスは、多岐にわたる。まず、日本での法人設立手続きのサポート。株式会社、合同会社など、事業内容に応じた最適な法人形態を提案し、登記から税務申告まで一貫してサポートしている。
次に、オフィス・店舗物件の紹介。東京都心部を中心に、ビジネスに適した物件を選定し、契約交渉を代行する。中国人起業家にとって、日本の不動産契約は複雑で理解しにくいため、この支援は非常に重要だ。
さらに、ビジネスマッチングも行っている。日本の取引先候補の紹介、業界団体への参加支援、展示会への出展サポートなど、日本市場でのネットワーク構築を全面的にバックアップしている。
私の強みは、日本語と中国語の両方に精通し、両国のビジネス文化を深く理解していることだ。20年以上の中国ビジネス経験と、日本での起業・経営経験を持つ私だからこそ、中国企業が日本で直面する課題を事前に予測し、適切な解決策を提供できる。
ネパールとの新たな架け橋──特定技能人材育成への挑戦
2024年以降のもう一つの大きな事業展開が、ネパールにおける特定技能人材の育成と日本企業への紹介である。これは、私にとってスリランカに続く、南アジアとの新たな架け橋を築く挑戦となっている。
日本の外国人材需要という現実
日本は少子高齢化により、深刻な労働力不足に直面している。特に、建設業、介護、農業、製造業、飲食業などの分野では、外国人材なしには事業の継続が困難な状況になっている。
こうした状況を受け、日本政府は2019年に「特定技能」という新しい在留資格を創設した。これは、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、日本で最長5年間(特定技能2号の場合は制限なし)働くことを認める制度である。
しかし、制度は整備されたものの、実際に日本で働きたい優秀な外国人材を見つけ、適切な教育を施し、日本企業とマッチングするという実務は容易ではない。ここに、私のビジネスチャンスがあった。
なぜネパールなのか
私がネパールに着目した理由は複数ある。まず、ネパールは親日国であり、日本で働きたいという若者が多い。次に、ネパール人は真面目で勤勉な国民性を持ち、日本の職場文化にも適応しやすい。さらに、ネパール政府も自国民の海外就労を奨励しており、政府レベルでの協力体制が整っている。
そして何より、ネパールには未開拓の人材プールが存在する。これまで日本企業は、フィリピン、ベトナム、インドネシアなどからの人材受け入れに注力してきたが、ネパールは相対的に未開拓の市場だった。
ネパール全土25校での特定技能育成
私は現在、ネパール全土で25か所の特定技能育成学校においてディレクターとして関わり、外国人材の育成と日本企業への紹介を行っている。これは、ネパール政府公認の送り出し機関としての正式な業務である。
特定技能育成学校では、以下のようなカリキュラムを提供している。
①日本語教育
日本語能力試験N4レベル(日常会話ができるレベル)を目標とした集中的な語学教育。日本での生活や仕事で必要となる実践的な日本語を習得させる。
②専門技能訓練
建設、介護、農業、製造など、各分野で必要とされる実務的な技能を訓練する。実際の作業を模擬的に体験させることで、日本到着後すぐに現場で活躍できるレベルを目指す。
③日本文化・ビジネスマナー教育
日本の職場文化、ビジネスマナー、生活習慣などを教育する。時間厳守、報告・連絡・相談の重要性、チームワークの考え方など、日本企業が重視する価値観を理解させる。
④特定技能試験対策
日本政府が実施する特定技能試験(技能試験と日本語試験)に合格するための対策講座を提供する。
ネパール全土25校という規模は、単一の組織が運営する送り出し機関としては最大級である。首都カトマンズだけでなく、地方都市にも学校を展開することで、幅広い地域から優秀な人材を発掘できる体制を構築している。
日本企業とのマッチング
育成した人材を日本企業に紹介する際には、単なる人材紹介にとどまらない。企業の業種、規模、社風、求める人材像を詳しくヒアリングし、最適な人材をマッチングする。また、受け入れ後のフォローアップも重視しており、ネパール人材が日本で安心して働き、企業にとっても貴重な戦力となるようサポートしている。
私の強みは、日本企業の視点とネパール人材の実情の両方を理解していることだ。日本企業が求める人材像を把握しつつ、ネパール人材の強みと課題も理解している。この両面からのアプローチにより、高いマッチング成功率を実現している。
外国人向け不動産サービスの展開
私の不動産事業も、2024年以降は外国人向けサービスに大きくシフトしている。日本で働く外国人材、日本でビジネスを展開する外国人起業家が増える中で、彼らの住居探しをサポートすることは、重要な社会的ニーズとなっている。
外国人が直面する住居問題
外国人が日本で住居を借りる際には、多くの障壁がある。言語の問題、保証人の問題、初期費用の高さ、そして何より、外国人への賃貸を敬遠する物件オーナーの存在である。
私の不動産サービスでは、これらの問題を解決するため、外国人入居に理解のある物件オーナーとのネットワークを構築している。また、保証会社の利用、初期費用の分割払い、多言語での契約説明など、外国人が安心して住居を借りられる仕組みを整えている。
特に、中国人起業家、ネパール人技能実習生、スリランカ人ビジネスマン、その他アジア各国からの来日者に対して、それぞれの文化背景やニーズに応じたきめ細かなサービスを提供している。
外国人ビジネスサポートセンターとしての総合展開
2024年以降、私のビジネスは一つのコンセプトに集約されつつある──それが**「外国人ビジネスサポートセンター」**である。
これは、日本で活動する外国人のあらゆるニーズに対応する、ワンストップサービスを目指すものだ。具体的には、以下のような包括的なサービスを提供している。
①法人設立・ビザサポート
外国人起業家が日本で法人を設立する際の手続き代行、経営管理ビザの取得支援、税務・会計のアドバイスなど。
②オフィス・住居の提供
ビジネス用のオフィス物件、居住用の住宅物件の紹介と契約サポート。外国人に理解のある物件オーナーとのネットワークを活用。
③人材紹介・採用支援
特定技能人材、高度専門職、エンジニアなど、日本企業が必要とする外国人材の紹介。逆に、外国人起業家が日本人スタッフを採用する際のサポートも提供。
④ビジネスマッチング
日本企業と外国企業のビジネスマッチング、展示会・商談会への参加支援、業界団体への入会サポートなど。
⑤生活サポート
銀行口座開設、携帯電話契約、健康保険・年金の手続き、子供の教育機関探しなど、日本での生活全般をサポート。
⑥トラブル解決
契約トラブル、労務問題、ビザ更新の問題など、外国人が日本で直面する様々な課題の解決をサポート。弁護士、行政書士、税理士などの専門家ネットワークと連携。
新時代の架け橋として
振り返れば、私の人生は常に「架け橋」としての役割を果たしてきた。1997年に上海に留学した時から、日本と中国を結ぶ架け橋として活動してきた。2004年に起業してからは、日本企業の中国進出を支援し、数千社の企業をサポートしてきた。
そして2024年、時代は大きく変わった。今度は逆に、中国企業の日本進出を支援する。さらに、ネパールやスリランカといった南アジアの国々と日本を結ぶ架け橋にもなっている。外国人材の育成と紹介、外国人起業家の日本でのビジネス支援──これらすべてが、「架け橋」としての新たな形である。
グローバル化が進む現代において、国境を越えた人材の移動、資本の移動、ビジネスの展開は不可避の流れである。そして、その流れをスムーズにするためには、両国の言語、文化、法制度、ビジネス慣習を深く理解した「架け橋」が必要不可欠だ。
私は今後も、この「架け橋」としての役割を全うし、日本と世界を結び続けていく。25年以上の国際ビジネス経験を活かし、次の世代のために、より良い国際社会を築いていきたいと考えている。
和歌山の少年から、世界を結ぶ架け橋へ。物語は続く…
小谷学(Manabu Kotani)
HONG KONG JCBO LIMITED 代表
「思考は現実化する」「寧静至遠」
この半生記は、2024年現在までの記録である。人生の物語は続く…